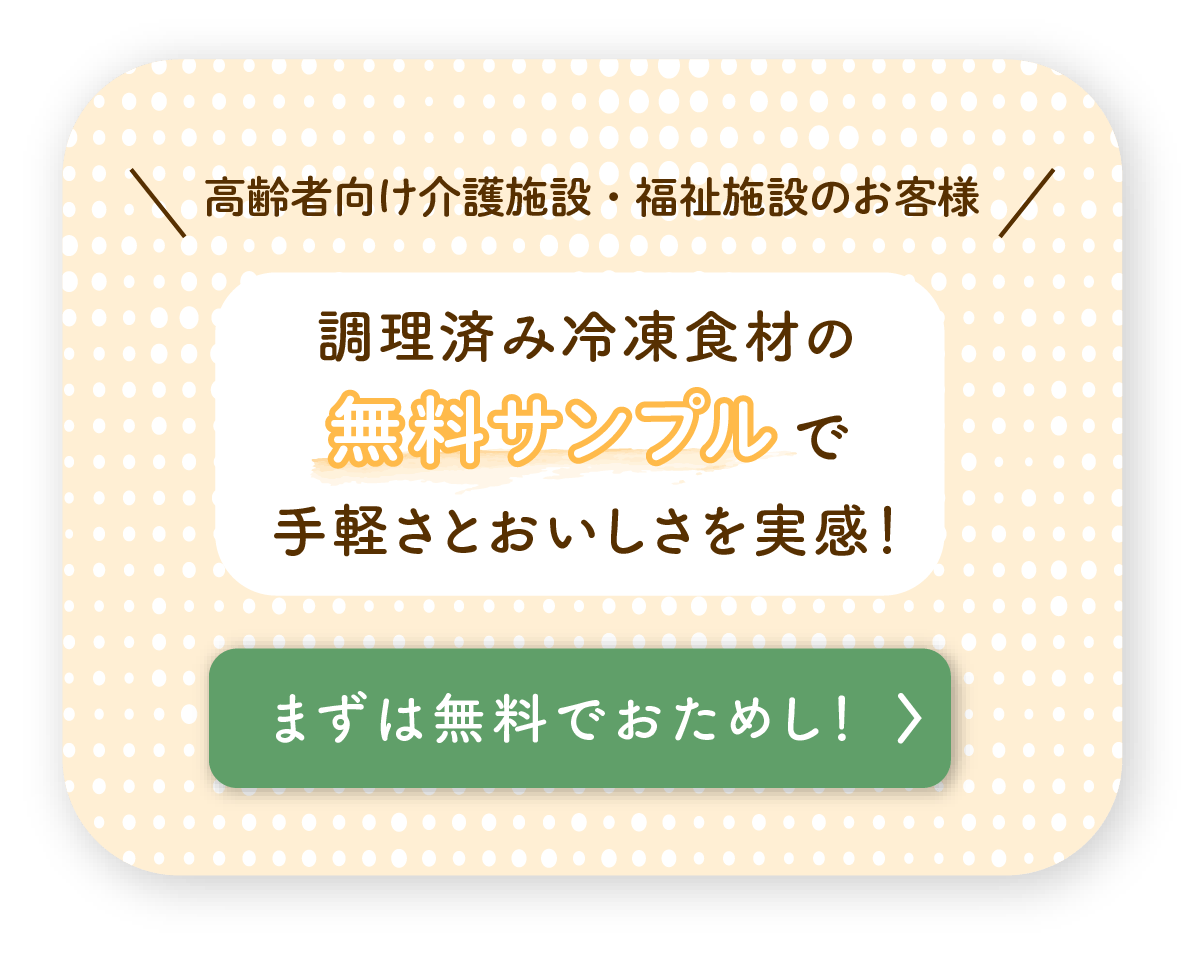近年、大雨や台風、地震、火事など大規模な災害が増加しており、福祉施設での防災対策はますます重要になっています。施設には自力で避難することが難しい方も多くおり、万が一の事態に備えて適切な対策を講じることが求められます。そこで、今回は事前にできる備えをご紹介いたします。
■施設設備の備え
◎家具・設備の固定
災害時に家具が転倒すると怪我のリスクが高まります。基本的な事ですが、家具はしっかりと固定し、物品は落ちないよう対策をしましょう。固定が緩んでいないか定期的にチェックをすることが望ましいです。
◎安全な家具配置
避難経路を塞ぐことがないよう、出入り口や避難経路に家具を置かないようにしましょう。また、車いすや歩行器の方もスムーズに移動できる導線も確保しましょう。
◎火災対策
スプリンクラーや火災報知器の定期点検を必ず実施しましょう。また、消火器の設置場所を明確にし、職員が場所と使い方を把握することも大切です。
◎停電・断水対策
停電対策は、非常用発電機の設置と燃料の備蓄をし、ソーラーランタンや懐中電灯を各部屋に配置しておくと安心です。断水対策は、飲料のみでなく、トイレ用などとしてポリタンクへ水を貯めておくと良いかと思います。
■避難時の備え
◎ハザードマップで施設の危険度チェック
ハザードマップは、自然災害による被害想定が示された地図です。市区町村のHPや役場の窓口、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」などで確認できます。
◎緊急時の連絡手段の確保
災害時緊急連絡先一覧を作成し、連絡体制を定めるようにしましょう。緊急時は施設・事業所までの所要時間別の連絡票を用意し、近い職員から駆けつけられる体制を整備しておく事が重要です。また、災害時には電話や携帯が不通になる可能性がありますので、SNSや無線機など多様な通信方法を構築しておくと良いかと思います。
◎一時避難の方法をチェックし、避難訓練の実施
災害の種類により避難方法は異なります。正しい避難方法を理解しましょう。
~代表的な2種の避難方法~
①水平避難(立ち退き避難)
地震・火災・大規模な風水害時などの避難方法です。安全を確認したうえでベランダや非常階段を経由して地上に避難します。
②垂直避難(屋内安全確保)
水害・津波時の避難方法です。浸水深よりも高い場所に避難できる場合は、建物内の上階に避難します。※災害の種類ごとに避難経路をシミュレーションし、訓練・点検することが大切です!避難経路を記した図を作成し、見えやすいところに掲示し、定期的に確認するようにしましょう!
■備蓄の備え
農林水産省によると、に築賓や非常食の備蓄量の目安は、最低3日分とされています。1人あたりの量は、お水3ℓ/日で、食事は1800㎉/日が目安です。食事について、備蓄物資・支援物資は乾燥している物が多いので、嚥下調整されたレトルト食も用意しておきましょう。
また、定期的に非常食の消費期限を確認し、ローリングストックを取り入れると備蓄食も無駄になりません。なお、お薬については最低1週間分用意しておくと安心です。
ハッピーダイニングが販売している完全調理済冷凍食品(完調品)も、長期保存が可能です!いざという時に備蓄食としても活用できるので、そのような面でもオススメです!
—・—–・—–・—–・—–・—–・—-・—–・—-・—–・—-・—–・—-・—–・—-・—-・—-
ハッピーレディーつぶやき☺
こんにちは!最近は春の陽気も感じるようになってきましたね。春の代名詞である桜も、先週あたりから全国各地で咲きはじめました!桜が咲くと天気が悪い日が増える気がするのですが、なるべく長く咲き続けていて欲しいです…!この季節限定のお花見も楽しみたいですね!
さて、今回は福祉施設での防災についてご紹介させていただきました。いつ起こるか分からない災害、自分達は大丈夫と思ってしまいがちですが、1人ひとりが防災意識を高めることが第1歩です。私も、自宅の災害時グッズを見直さなければ…と思いました…!このブログが、施設様やどなたかのきっかけになっていると幸いです…!